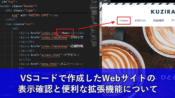マーケティングの基本について
マーケティングの定義は人や立場によって様々ですが、ここでは「商品・サービスを売るための仕組み作り」と定義しています。
物を作るだけで売れていたのは昔の話で、今では「顧客のニーズに合ったもの」「顧客の悩みを解決してくれるもの」でないと、なかなか売れにくい時代となっています。
また競合も多く、そんな中でも生き残っていくためには、「顧客に認知されて選ばれる」ことが必要となり、そのための仕組みとして「マーケティング」が必要不可欠となってきています。
ここでは、そんな「マーケティング」の基本について紹介していきます。
この記事の目次
「誰に?」「何を?」「どのように?」
マーケティングとは「商品・サービスを販売する仕組み作り」と定義しましたが、大きく分けて3つの項目に対して考えていきます。
- ターゲット(誰に?)
- 商品・サービス(何を?)
- 販売方法・認知(どのように?)
もちろん他にもありますが、基本的にはこの3つを軸として仕組みを作っていきます。
ターゲット(誰に?)
まず最初に考えるべきは「誰に売るのか?」という、マーケティング用語でいうところの「ターゲット設定」です。
不特定多数の人に声をかけても誰も振り返ってくれないように、明確なターゲット・条件を設定することで、その人の心に刺さりやすくなります。これが「ターゲティング」です。
このターゲットを決める時に「抱えている悩みやニーズ」はもちろん、年齢や性別、職業や収入、居住地などを絞りこむことでより具体的なターゲット像が出来てきます。
この設定を一人の架空の人物が出来上がるまで絞り込んだものを、マーケティング用語で「ペルソナ」と呼ばれています。
ペルソナの事例①:30代ワーママ向けのオンライン英会話
商材ジャンル:教育・語学(オンラインサービス)
- 名前:佐藤 美咲(さとう みさき)
- 年齢:34歳
- 性別:女性
- 居住地:東京都内のマンション
- 職業:IT企業の時短勤務・マーケティング担当
- 家族構成:夫と5歳の子ども
- 年収:450万円
- 課題・ニーズ:
- 忙しくても子どもの英語教育に時間を割きたい
- 自分もキャリアアップのために英語力を伸ばしたい
- 通学型のスクールに通う余裕がない
- 価値観・行動特性:
- 家事・育児と仕事の合間にスマホで学べるものを好む
- SNSで口コミをよく確認する
- 成果が数字で見えるサービスに信頼感を持つ
ペルソナの事例②:中小企業の経営者向けクラウド会計ソフト
商材ジャンル:BtoB SaaS(クラウド型業務支援ツール)
- 名前:山本 隆志(やまもと たかし)
- 年齢:46歳
- 性別:男性
- 居住地:大阪府堺市
- 職業:建設会社の経営者(従業員12名)
- 年収:700万円(自社役員報酬)
- 課題・ニーズ:
- 確定申告や決算業務の効率化
- 会計士に丸投げではなく、ある程度自分で把握したい
- 出先でも数字を見られる環境が欲しい
- 価値観・行動特性:
- ITには少し苦手意識がある
- コストにはシビアだが、業務効率には投資を惜しまない
- 知人の紹介や展示会の情報をよく参考にする
ペルソナの事例③:20代女性向けのオーガニックコスメECサイト
商材ジャンル:美容・EC(D2Cブランド)
- 名前:小川 舞(おがわ まい)
- 年齢:27歳
- 性別:女性
- 居住地:福岡県福岡市
- 職業:アパレル販売員
- 年収:280万円
- 課題・ニーズ:
- 肌荒れが気になり、自然派のスキンケアに興味あり
- インスタなどで情報を集めて、パッケージにも敏感
- コスパの良いアイテムを探している
- 価値観・行動特性:
- SNSで美容系インフルエンサーの投稿をチェック
- 写真の世界観や「映える」かどうかも重視
- 定期購入は少し抵抗があるが、トライアルは興味あり
ターゲットを絞るメリット
ターゲットを絞ることによるメリットは「その人に深く刺さりやすくなる」というのに加えて、意外かもしれませんが「その属性に近い人にも刺さる」というメリットがあります。
また、ターゲットに深く刺さるほど、『これは自分のことでは?』と感じ、振り向いてもらえる、または行動(購入)に移してもらえる可能性が高まります。
もちろん振り返ってもらう(=認知される)ことが無い限り商品も売れないので、ターゲティングを行う時はできる限り絞るようにしましょう。
商品・サービス(何を?)
ターゲットを決めたら、次に商品・サービスを設定します。
大前提として、それがターゲットの悩みを解決できるものであることが重要です。
さらに「その商品を使うとどうなるのか?」という“ベネフィット(利益・未来像)”を明確にすることも大切です。
顧客は、商品そのものよりも「ベネフィット(この商品・サービスで得られる利益・未来像)」に価値を感じることがあるのですが、中には潜在的なニーズに気づいていない人もいるため、しっかりとベネフィットを掲示(言語化)して伝えることが重要です。
これらを踏まえて商品を設定する時に「ポジショニング」や「マーケティングミックス」と呼ばれる施策を使って決めていきます。
ポジショニング
マーケティングにおける「ポジショニング」とは、競合との差別化を図り、自社の立ち位置を明確にするための手法です。
また、「どの要素で差別化を図るのか?」が重要で、競合他社のリサーチをしっかりと行う必要があります。
マーケティングミックス
マーケティングミックスとは、戦略を構築するために複数の要素を組み合わせる手法です。「4P」「4C」などのフレームワークがあります。
4P(企業視点)
- Product(商品・サービス)
- Price(価格)
- Place(販売経路)
- Promotion(広告・宣伝)
4C(顧客視点)
- Customer Value(顧客価値)
- Cost(費用)
- Convenience(利便性)
- Communication(顧客対話)
これらをバランスよく考慮しながらマーケティングの仕組みを作ることで、ターゲットのニーズ・悩みをくみ取った商品やサービスを販売しやすくなります。
販売方法・認知(どのように?)
どんなに優れた商品でも、認知されなければ売れません。販売経路やプロモーション方法の設計も非常に重要です。
「どこで売るか?」だけではなく、「どうやってそこまで来てもらうか?」という導線設計を意識しましょう。
販売方法の設計
販売方法には、ECサイト、資料請求後の営業、対面販売などさまざまな形があります。
上記と重複しますが、マーケティングでは「どこで売るか?」というより、「その販売場所までどうやって来てもらうか?」を考えることが重要です。
どの方法であっても、購入までの導線がスムーズであることが重要です。煩雑なプロセスは離脱につながるため、可能な限りシンプルでわかりやすい経路を用意しておくことが大事です。
認知施策の具体例
認知度を上げるための施策として、以下のようなものがあります。
- チラシ・ポスティング・フリーペーパーなどの紙媒体
- ネット広告(Google広告、SNS広告など)
- SEO(検索エンジン最適化)
- SNS運用(Instagram、X、TikTokなど)
いずれも認知につなげるにはそれなりに効果がありますが、大事なのは上にも書いたように、それらから販売場所に来てもらうことです。
この経路を「集客導線」と呼び、販売場所から逆算してこの経路を事前に考えておくと良いでしょう。
マーケティングは事前に考えること・調べることが多く、慣れるまでは大変な作業です。
しかも、それが必ず成功するとも限りませんし、はじめの頃では失敗することの方が多く、先に心が折れてしまう場合もあるかと思います。
ですが、マーケティングは最初こそ難しく感じるかもしれませんが、実践を通じて着実に身につくスキルのため、資格よりも実践的で、あらゆる業界で応用可能な知識なので、ぜひ習得していきましょう。