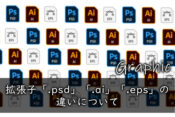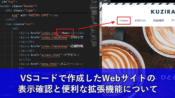「デザイン」と「アート」の違いは「目的」にある
「Webデザイナー」や「グラフィックデザイナー」という名前を聞いて、おそらく大半の人はこのようなイメージをするかと思います。
「自分の好きなデザインを生み出して形にする人」
これは間違っているわけではありませんが、実際のデザイナー像とはちょっと違う部分があります。
そのヒントとして「デザインとアートの違い」を使ってお伝えしていきたいと思いますので、今後の考え方としての参考にしていただけたらと思います。
デザインとアートの違い
一見どちらも同じような意味に思えるかもしれませんが、実は大きく異なります。
その大きな違いは「目的」にあります。
では、デザインとアートの「目的」とはそれぞれどのようになっているのか、順に説明していきます。
「デザイン」の目的
「デザイン」という言葉は「美しくする」や「かっこ良くする」など、見た目に関する意味合いがとられがちですが、「問題の解決」が本質的な意味だと言われています。
これはデザイン会社で働く場合でも、フリーランスで仕事をする場合でも同じで、顧客(クライアント)が抱えている問題を解決するのが「デザインの本質」であり、「主な仕事」となります。
また、デザインという言葉の意味の中に「設計」というのも含まれています。
これを「問題の解決」と照らし合わせると、
問題を見極め、それらを解決していく過程や計画も含めて「デザイン」となります。
その結果として「使いやすい」「わかりやすい」「スッキリとした」「綺麗な」「魅力的な」といった見た目の部分に現れてくるのですが、一般の人はその過程がわからない(見えない)ため、見た目に関する意味合いとしての「デザイン」として捉えられているのかもしれません。
「アート」の目的
「デザイン」の目的が「問題の解決」なのに対し、「アート」の目的は「自己表現」だと言われています。
自分の中にあるものを表現し、それを理解してくれる人もしくは共感してくれる人に巡りあることができれば、それがあなたの利益となります。
それは絵画であったり、音楽であったり様々な自己表現の手段があり、それらを使って自己表現する人を「アーティスト」と呼ばれています。
ここで気をつけておきたいのが、クライアントワークでの「アート的思考」はよくありません。
あくまでも「相手(クライアント)の問題を解決する」というのが大前提のため、悩みや問題、欲求を汲み取った上で問題解決につながるものを作る必要があるからです。
そこにあなたの意思(アート的思考)はほとんど無いと考えておいたほうが良いでしょう。
「デザイン」と「アート」の使い分け
この2つの違いを知ることで、「デザインとアートの使い分け」の重要性が理解できたかと思います。
そこで「デザイン」と「アート」をあなたの活動の範囲で使い分けるとしたら、
・「デザイン」→クライアントワーク、情報発信など、対外的なこと
・「アート」→ポートフォリオ、自分で所有するWebサイトなど、自分に関すること
といった感じで使い分けることができると思います。
この違いをよく覚えておき、今後の活動の参考にしていただけると幸いです。